Case 6
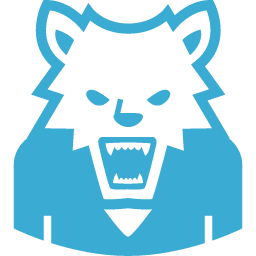
男性・32歳
ロシアのサーカス団の子供として生まれた私は、赤子の頃から興行で世界を旅していました。
流浪の暮らし故、友人はおらず、心が通う相手はクマのモストボイだけ。
芸のためとはいえ、親友のモストボイに鞭をふるわなければならず、そのジレンマに心を痛めた私はすっかり塞ぎ込んだ少年となっていました。
16歳のとき、日本のカスカヴェという街を興行で訪れました。
テント裏の草原でいつものように鞭の素振りをしていると、カスカヴェの同年代と思しき少年たちが歩み寄って来たのです。
そして、「ダンチョウ」と名乗るリーダー風の少年が屈託のない笑顔で私に話しかけました。
『キミ、なに怖い顔をして鞭をふるっているんだい?よかったら僕らと一緒にサッカーしよう!』
私は誘われるがままに草原で彼らとともにフゥドゥボール(ロシア語でサッカーの意)をしました。
初めての同年代の少年たちとの触れ合いは、ツンドラのような私の心を瞬く間に溶かしました。
それから、カスカヴェに滞在していた数週間、毎日彼らとボールを追いかけたのです。
日本を離れる日、ダンチョウはボールを渡しながら私に言いました。
『いいかい?キミはどこへ行っても鷹の団の一員だ。いつでも戻って来い。スヴィダーニャ(さようなら)は言わないぜ!』
その後、私は芸に精進し、世界でも有数のサーカス団の団長となりました。
今では以前にも増して世界中を慌しく旅していますが、ふと、あのカスカヴェでの夢のような日々を思い出すのです。
いつまでたっても、鷹の団は私の心の拠り所なのです。
~ロシアより愛を込めて…
(この文章はフィクションです)
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から
